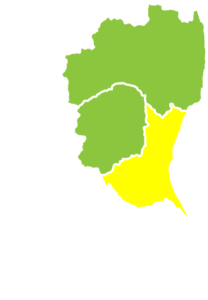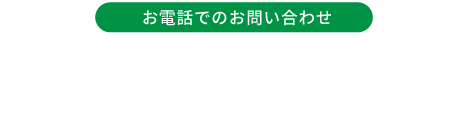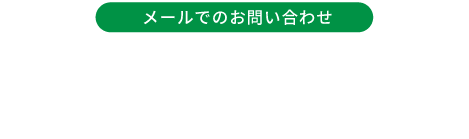共有持分の相続は慎重に!後々のトラブルを防ぐためのポイント

相続時に、不動産を「共有持分」にするケースがよく見受けられます。しかし、共有にすることで、後々複雑な問題が発生する可能性があります。本記事では、共有持分の相続に伴う問題点や注意点、解決策について詳しく解説します。

共有持分の相続がもたらすリスク
1. 相続人が増えることで手続きが複雑化
共有持分にした相続人のうち誰かが亡くなった場合、その相続人の家族や新たな相続人が登場します。そのたびに戸籍をたどり、新たな手続きが必要になります。
2. 売却や利用の合意が難しい
共有名義の場合、不動産の売却や利用に関して、全員の同意が必要です。一人でも意見が合わないと、スムーズに進みません。
3. 法的手続きが受けられないケースも
共有者が多すぎたり、戸籍をたどるのが困難な場合、司法書士が依頼を受けられないケースもあります。このような状況では、さらに解決が難しくなります。
共有持分相続を防ぐためのポイント
1. 相続権利者同士で話し合う
相続前に、全員が納得できる形で不動産の分割方法や管理方針を決めることが重要です。
2. 共有を避ける方法を検討
- 不動産を売却して現金で分割する
- 特定の相続人が単独で所有し、他の相続人に代償金を支払う
3. 専門家に相談する
司法書士や弁護士、不動産コンサルタントに相談することで、適切なアドバイスを受けられます。手続きの進め方や最適な方法を提案してくれるでしょう。
共有相続で困っている方へのサポート
もし、すでに共有持分が発生している不動産をお持ちの場合でも、解決策はあります。
- 持分の買い取り 弊社では、共有持分の不動産の売却や買取に対応しています。お困りの場合はお気軽にご相談ください。
- 専門家の紹介 司法書士や弁護士との連携を通じて、解決までのサポートを行っています。
あわせて読みたい


相続登記の義務化について
2024年4月1日から、相続登記の義務化が施行されました。この改正は、日本の不動産登記制度における大きな変革の一環であり、多くの人々にとって重要な影響を及ぼします…
まとめ
共有持分で相続することは一見公平に思えますが、後々の手続きや利用面で大きな負担を招く可能性があります。相続権利者同士で話し合い、専門家の意見を取り入れながら、最適な方法を選ぶことが重要です。
相続や不動産に関するお悩みがございましたら、ぜひ私たちIIK株式会社までご連絡ください。
📞 お問い合わせ先
TEL/FAX: 0295-55-8829
携帯: 090-7939-6618
✉️ Email: uranaipom@yahoo.co.jp
共有持分の問題を解決し、安心した相続を実現しましょう!
この記事を書いた人 石川実(ishikawa minoru)
ひたちハウス、IIK株式会社代表。
宅地建物取引士
空き家空き地の買取、リフォーム賃貸を手掛けるひたちハスウ、出張買取販売「出張リサイクルショップ24時」など茨城県内地域密着でお客様の悩みを解決するべく様々な事業を展開。プロの目線で空き家、空き地の管理方法等を伝授します。